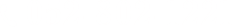肛門嚢アポクリン腺癌
肛門嚢にできる比較的まれな腫瘍です。皮膚腫瘍全体の約2%と言われています。雌犬に多いとされていたが、最近は性差が無いと言われています。犬でみられる事が多く、猫での発生はまれです。
非常に局所浸潤性強く転移しやすいと言われています。発見時に約50%の症例で腰下リンパ節群に転移がみられると言われています。
腫瘍が原因の高カルシウム血症がみられることがあり、多飲多尿や元気消失、歩様異常等の症状がみられる事もあります。(腫瘍から上皮小体ホルモン関連タンパクが放出される為)
腫瘍の物理的な影響により、肛門周囲が膨らんできたり、腫瘍の転移によるリンパ節の拡大は大腸を圧迫して、便秘、便の形の変化がみられます。時に排便困難に陥ることもあります。
診断
臨床所見と細胞診で、肛門嚢アポクリン腺癌を予想出来ます。しかし、確定診断は切除後の病理組織学的検査で行います。肛門周囲の観察や直腸検査、超音波検査での腰下リンパ節の確認が必要です。(リンパ節の転移病巣や高カルシウム血症からこの腫瘍を疑うこともあります。)
浸潤性増殖の有無などの構造異型が細胞診では確認できないため、犬の肛門周囲腺に発生する腫瘍の確定診断には細胞診は不向きです。しかし、腫瘤自体が、肛門周囲腺に関係したものか、それ以外の物かを確認するためには細胞診は有効です。
超音波検査で局所リンパ節、肝臓、脾臓などへの転移の有無を確認します。レントゲン検査にて肺転移を確認する必要があります。
治療
外科手術
手術により腫瘍を摘出します。腰下リンパ節群に転移があっても手術適応となります。手術の際は腫瘍による全身状態への影響を最小限にするための準備が必要です。高カルシウム血症が存在する場合、生理食塩水による積極的な輸液や利尿剤の投与を実施し、カルシウムの排泄を促して全身状態を整えます。
腰下リンパ節群への転移があり、便秘がある場合、腫瘤摘出だけではなく、腰下リンパ節群の切除を考慮します。これにより排便困難の影響を緩和させることが出来るでしょう。
放射線治療
転移が認められる腰下リンパ節群への照射により転移の発生を抑えることが目的です。残念な事に緩和治療であり、根本的な完治には至りません。
また、手術が適応にならない場合の緩和目的で放射線治療を選択することもあります。ただし、放射線治療には頻回の全身麻酔、治療可能な施設が限られるなどの制限もあります。
化学療法
転移率が高いため、術後カルボプラチンやドキソルビシンやアクチノマイシンDなどの補助的化学療法が推奨されています。通常、化学療法単独では生存期間が短いため、通常外科手術との併用で実施される事が多いです。またチロシンキナーゼ阻害剤も外科治療と併用することによる効果が期待されています。
予後
腫瘍のサイズが大きいほど生存期間が短いと言われています。高カルシウム血症の有無や、肺転移の有無、外科療法単独、化学療法単独、外科化学療法併用等、治療法の選択によっても生存期間の違いが認められています。
一般的には外科手術に比べると、手術無し、化学療法のみは短い生存期間となっています。
膀胱移行上皮癌
膀胱移行上皮癌とは、犬の膀胱に発生する悪性腫瘍として最も多く認められます。発生部位は膀胱三角部という左右の尿管と尿道の接続部に場所に発生することが多く、手術方法や治療に対するアプローチが困難になることも珍しくありません。性差が認められ、雌での発生が多いと言われています。
猫でも膀胱に発生する悪性腫瘍としては移行上皮癌が最も多く見られますが、犬とは異なり、膀胱三角部以外での発生が多いとされています。
好発犬種はスコティッシュ・テリア、ビーグル、シェットランドシープドッグなどがあげられます。
環境因子として、除草剤、殺虫剤に触れることがあげられます。
症状は、血尿、頻尿といったいわゆる膀胱炎と同じです。従って長く続く膀胱炎様症状の場合、膀胱移行上皮癌の可能性を考え精査する必要があります。
また、稀に骨への転移や肥大性骨症という四肢の骨が厚くなってしまうことにより歩行異常を示す事があります。
診断
細胞診
膀胱や尿道の腫瘍を疑う場合は細胞診目的の尿採取でも尿検査を実施することが推奨されています。自然尿では細胞の良好な状態は期待できないことが多いため可能であれば、カテーテルにて採尿します。 正常な尿路の上皮性細胞が尿中に大量に剥離することはありません。炎症や腫瘍化によって細胞同士の接着性の低下した細胞が剥離して尿中に検出されます。
通常の尿検査では下腹部から針を刺して膀胱に針を到達させる方法(膀胱穿刺)もありますが、移行上皮癌が疑われる場合は、針を抜く際に腫瘍細胞が違う場所に移植されてしまうことがみられるので膀胱穿刺は禁忌です。
その他尿から分かる検査
V-BTA検査
自然排尿可の尿で検査が可能です。特徴としては、犬の膀胱移行上皮癌に特化した検査であることです。尿中のグリコプロテイン(腫瘍細胞が分泌した蛋白分解酵素が基底膜構造を分解した際に出てくる分解産物)ただし、尿中の赤血球や白血球の数が8mlの検体の場合400倍で10個以下でないと偽陽性の原因となってしまいます。(30個を超えると検体として不適)
この検査の感度は90% 特異性は78%。つまり陰性結果の信頼性は高いという検査です。
BRAF遺伝子変異検査
犬膀胱移行上皮癌及び前立腺癌に高い確率でみられる腫瘍細胞はBRAF遺伝子が変異する特徴を持っていることを利用した検査です。大体8割くらいの移行上皮癌と前立腺癌の腫瘍細胞はBRAF遺伝子の変異を認めます。その遺伝子変異をPCRにて検出する検査となります。
尿中に出現した細胞をPCR検査しBRAF遺伝子の変異が認められる場合、移行上皮癌あるいは前立腺癌の可能性がかなり高くなります。ただし、3割弱の悪性腫瘍細胞がBRAF遺伝子の変異を持たないと言われているため、陰性でも腫瘍を否定することにはなりません。
画像診断
CT・超音波検査・レントゲン検査では腰下リンパ節の腫大、前立腺肥大、骨格への転移(特に腰椎)の発見が可能です。
犬の場合は殆どが膀胱壁の筋層に浸潤する「表在性乳頭状腫瘍」や膀胱壁に浸潤した病変を示します。約6割弱が尿道へ拡がりを見せ、約三割弱が前立腺へ拡がりを見せます。膀胱内腫瘤では膀胱漿膜の平滑が保てているか、膀胱の漿膜面に不整が認められないかを調べます。漿膜面に不整が見られるばあいは膀胱壁の外にまで腫瘍が達している可能性があります。
膀胱三角部を含む膀胱頚部近くに腫瘍では、尿管開口部障害による水腎や水尿管が生じている場合もあるため、超音波で腎臓、尿管も合せて評価を行います。
さらに排便困難を呈する動物では、膀胱腫瘍の尿道浸潤、尿道粘膜の原発性腫瘍、前立腺癌などが疑われます。
治療
外科的治療
膀胱全摘出術及び尿路変更術
根治的治癒の可能性が最も高い手術方法です。膀胱を摘出してしまうことにより尿を貯めることが出来なくなり、持続的に排出される尿の管理や手術自体の難易度、侵襲性など問題点も多い手術方法です。
膀胱部分切除術
膀胱の腫瘍が存在している部分のみを摘出する方法です。かなり大きくマージンをとっても他の部位にも腫瘍細胞が存在している可能性が高く、再発する可能性が高いため、根治的ではなく、緩和的治療と位置づけられています。
尿管ステント、尿道ステント
膀胱移行上皮癌は膀胱三角部に発生することが多く、尿管開口部が腫瘍により閉塞され、水腎症から腎不全を起こすことがあります。その予防として尿管ステントが設置されることがあります。これも緩和的治療の一つとなります。
化学療法
ミトキサントロン及びピロキシカム又は、ドキソルビシン及びピロキシカムの併用が推奨されています。
(ピロキシカム単独使用でも約2割は一年以上生存可能という報告もあります)
犬の精巣腫瘍
犬の精巣腫瘍は去勢をしていない雄犬において2番目に多い腫瘍と言われています。生後、陰嚢内に精巣が降りてきていない潜在精巣の犬は、正常に精巣が下降した犬と比べて精巣腫瘍になるリスクが約9倍高いと言われています。
犬の精巣腫瘍は大別すると3つに分けることができます。
セルトリ細胞腫、精上皮腫(セミノーマ)、間質細胞腫(ライデッヒ細胞腫)
の3種類の腫瘍に分類されます。
間質細胞腫(ライディッヒ細胞腫)>セルトリ細胞腫>精上皮腫(セミノーマ)の順序で発生率が高いと言われています。
何れの精巣腫瘍も多臓器への転移リスクは高くありません。
セルトリ細胞腫
セルトリ細胞腫の症状として、雌性化や対称性脱毛、貧血が見られることがあります。 また、高エストロジェン血症による二次性再生不良性貧血が腫瘍随伴症候群として知られています。過剰なエストロジェンは胸腺間質細胞に働き、骨髄抑制物質を産生させることにより血球減少症を引き起こすと言われています。 血球減少症は顆粒球減少症から始まるか、急速に多能性幹細胞の消失が起こり、汎血球減少症へと進行します。特徴的な末梢血所見は、著明な好中球減少、血小板減少、非再生性貧血です。
精上皮腫(セミノーマ)
潜在精巣で発見されることが多い精巣腫瘍です。高エストロゲン血症に伴う症状が認められる事があります。
間質細胞腫(ライディッヒ細胞腫)
間質細胞腫は1cm以下の小さな結節であることが多いです。よって、たまたま発見されるケースが多いです。
セルトリ細胞腫やセミノーマの様に高エストロゲン血症はあまり多くありません。
診断
切除生検
外科的切除が唯一の治療方針である場合は治療を兼ねた生検が行われます。腫瘤を丸ごと切除して病理組織学的評価を行います。ただし、適応は腫瘍組織が完全に切除できる場合に限られます。
治療
手術による摘出がもっとも有効です。転移の可能性が少なく摘出により根治が期待できます。浸潤が無い腫瘍では、開放法の精巣摘出術も選択されるが、周囲浸潤が疑われる場合は、総鞘膜ごとの切除(閉鎖法)や陰嚢切除術が適応となることがある。 もしも転移が認められる場合は、転移部位の外科的切除も考えなければなりません。場合によっては放射線治療や化学療法による治療が必要となる場合があります。
化学療法はシスプラチンの全身投与および、腹腔内投与が効果を示しています。 転移したセルトリ細胞腫とセミノーマには、シスプラチン、ブレオマイシンが奏功した少数の報告があります。
予後
外科手術による治療が完了すれば予後は良好です。 転移の可能性が低いため原因の精巣を摘出することで根治的治療となります。発見時に遠隔転移、リンパ節転移、血球減少症等の症状を認める場合はその後の治療が重要になってきます。